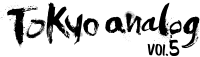小説家の役割は、下すべき(最低限の)判断を
もっとも魅惑的なかたちにして読者にそっと手渡すことにある
── 村上春樹 ──

「ヨシダさん……ですか?」
ミカコと名乗る女は、電鉄会社が運営する、大井町駅中央口からすぐそばにある小ぎれいなビジネスホテルのロビーのソファに座っているぼくに、背後からこう声を掛けてきた。
女は30代後半から40代前半あたりの年頃で、身長からも容姿からも肉付きからもメイクにも際立った特徴を見いだすことができない、いわゆる地味めなタイプだった。膝丈くらいの紺のワンピース姿で、小ぶりなサイズの真珠をアクセントとするゴールドチェーンのネックレスが、控えめに胸を飾っていた。ぼくは白いVネックのTシャツをインナーにして、3年ほど前に御殿場のアウトレットのHUGO BOSSで購入した一張羅の黒いスーツを着ている。「できれば遊びにも冠婚葬祭にも使えるものを」という貧乏臭い理由で選んだ、葬式用にはさすがにきびしい、光沢感が強いウール素材でつくられた細身のスーツで、値段は上下総額で8万円するかしないかだったと思う。まだ10月初めの陽気には季節外れで首筋にうっすら汗がにじんでくるが、一張羅なのだからしかたない。
半年前の4月、ぼくがウェブデザイナーとして専属契約していた新進のIT企業がなんの前ぶれもなく倒産し、CEO、COO、CFOの肩書きが名刺に刷られた3人の幹部連中は全員夜逃げした、らしい。
当然、すでに納品した仕事のギャラは振り込まれず、クレジットカードやキャッシングでしのげるその場をしのいでいたものの、ぼくは現金に困っていた。とりあえずは、一週間後に約20万円の支払いが迫っているのだ。
途方に暮れたぼくは気がつくと、渋谷の裏通りに雑然と建ち並ぶ怪しげな貸しビルの壁面に貼ってあった「出張ホスト募集」のビラに記載されている電話番号を半ば夢遊病者ごとくタップしていた。もし、必要経費などと手付け金のような前払いを請求されたり、「研修」と称する面倒な召集を強要されたりしたら、その時点で断りを入れるつもりだった。ビラ上には「週1回でも可」「1日4時間以下勤務」「月収30万以上保障」……と、お決まりのキャッチコピーが、けばけばしくおどっている。

臆病なまでに身構えるぼくの予想に反し、入会はあっけないものだった。前払いも研修もなく、面接すらネットでのやりとりだけで済んだ。「女性の嫌がる行為はやめてください」「連絡先の交換は厳禁」ほか、いくつかの簡単な注意事項に、ここ数日のスケジュールや報酬の受け渡し方法の確認のみで、申告したぼくの個人情報も、プロフィール写真以外はほぼでたらめだ。「こんなに杜撰で大丈夫なのか?」と、別の不安が頭をよぎる。
入会後わずか2日後に、いきなり依頼の電話がかかってきた。
「ミカコさんという女性が、ヨシダさん(もちろん偽名だ)をご指名されたので、明日の18時に大井町駅の○○ホテルのロビーへ来てもらうことは可能でしょうか?」
快活と事務的のバランスが絶妙な、20代にも50代にも聞こえる男性の声だった。
「大丈夫です。ぼく当日黒いスーツを着ていく予定で、年齢は42歳ですけど、見ためは30代だと周囲からはよく言われます」と答えたら、「そうなんですか」と苦笑混じりに流された。肩の力が抜け、ぼくは軽口をつづける。
「新宿の京王プラザだとか六本木のマンダリンとかを想像していたんですけど……大井町って、かなりマニアックですよね?」
「先方様のご都合なので……」
「それにしても、こういうのって本当にホテルのロビーで待ち合わせするんですね?」
「なんだかんだ言って、ホテルのロビーはこういう待ち合わせに最適なんですよ」
「まずは食事に行きますか?」
できるだけの優しい口調でぼくは訊ねてみる。すると、ミカコと名乗る女はうつむきながらかすかに首を横に振り、こう短くささやいた。
「最初からホテルでいいです……」
「上の部屋を取っているんですね」
「いや、歩いてちょっとのところにラブホテルがありますから……」

ロビーを出て、ミカコと名乗る女の半歩あとを、ぼくは無言のままついていく。肩でも抱いたほうが良いのかと迷いもしたが、やめておいた。ぎこちない空気は動かすよりもキープしておいたほうがやや無難だ、と瞬時に判断したからだ。
大井町駅の中央口から西口まで徒歩で移動して、京急の青物横丁駅方面に向かう商店街を通り、ゼームス坂を左に折れる。なぜこのヒトはこうも一目散に、わき目もふらずにぼくをナビゲートできるのだろう、意外とこういうサービスを利用し慣れているのか、それとも住まいが近所なのか……そんなことを考えながら雑多な飲食店が並ぶ横丁を通りすぎてまもなく、車がぎりぎり一台入れるだけの幅しかない小径を、また右に曲がる。閑静で古い住宅街だ。こんなところにラブホが本当にあるんですか、と聞かずにはいられなくなったころ、左側に三階建ての、濃いクリーム色の壁面で窓の上に赤と白のツートンカラーで彩られた雨避けが付いた、まるでヨーロッパの田舎町にぽつんと佇む萎びたペンションのようなラブホテルが目に入り、ミカコと名乗る女がそのエントランスを躊躇する様子も見せずにくぐっていく。一応、ライトアップはされているものの、「この建物内にいるカップル全員がセックスをしている」というラブホテル独特の、ぐらぐらに煮立った天ぷら油が放つ熱気のようなオーラはまったく漂っていない。「OPEN」と「FULL」を青と赤で表示する電飾板は、早秋午後六時の闇空にもかかわらず、見分けがつかなかった。
ミカコと名乗る女は、電鉄会社が運営する小ぎれいなビジネスホテルのロビーで会ったときの印象に反して、均整がとれた滑らかな曲線がなまめかしい、完璧な身体の持ち主だった。肌も吸いつくように纏わりついてきて、しかも貪欲で、すぐさま猛烈に勃起する。
それでもぼくは何故かなかなかいけなかった。ちょうど、一つしか小便器がない公衆トイレで、後方に並ぶ行列を意識しながら用を足さねばならない感覚に似ている。射精が“強要”を通り越して“義務”と化している初めての経験に焦り、戸惑っているのかもしれない。

もはや集中力を欠いた状態で腰を振りつづけるぼくは、なにか難しいことを考えて、それを猥褻へと結びつけてみようと試みた。
100万年前に生きていた人類は、鋭く尖った石器を代表とする“道具”を使用していたにもかかわらず、大きな獲物を狩ることは稀で、おもに植物を集め、昆虫を捕まえ、小さな動物を追い求め、他のもっと強力な肉食獣が残した死肉を、たとえばライオンがキリンを倒しハイエナやジャッカルがその残り物を漁ってからの“おこぼれ”を食らっていたという。石器を代表とする“道具”の最大の用途の一つは、骨を割って中の骨髄をすすることだったのだ。長年、このように食物連鎖の中間を占めていた人類が頂点へと飛躍したのは10万年前のホモ・サピエンスの台頭に伴っており、その道のりにおける重大な進化とは「火を手懐けたこと」であった……道具に頼ってインターバルを……と、ふいにアイディアが浮かんだが、あいにく道具は持ち合わせていなかった。部屋の設置されている小型の冷蔵庫のような自動販売機で数種の道具は販売いてはいるものの、とてもじゃないが行為を中断してそれを購入する決断は、ぼくには下せない。あきらかにタイミングを逃している。また別の難しいことを懸命に脳内の引き出しからまさぐる作業を繰り返す。
ボノボは、まずメスが、相互に尻と性器をこすり合わせるような、ホカホカと呼ばれる性的接触をしたあとで獲得した蜂蜜を順番に分ける。争奪の競争や衝突は起こらない。食物分配の主導権はメスが握っている、オスには余剰分が最後に分配される。なんて素晴らしい世界なんだ……でも、やはりだめだった。空白となった思考のすき間を、逆に生理的現象の我慢を強いるシチュエーションの記憶がじわじわと潜り込み、やがて一つの大きな流れへと変わっていく。
とある週末の夜、とある男友だちの家へ遊びに行ったときの話だ。
ささやかな宅飲みパーティーがあるということで、ぼくはそこに急いで合流しようとしていた。その日は別の飲み会にも顔を出してきた直後で、最寄りの駅に着いたころは、すでに夜の11時を過ぎていた。

その彼の家は、駅から延びる真っすぐの道沿いにあって、Googleマップを使わずとも間違えようもなく、だが徒歩だと15分はかかってしまう、距離的には微妙な場所だった。最終のバスがなくなったのか、駅前ロータリーのタクシー乗り場には行列ができている。
酔い醒ましにいいな、と歩いて行くことにした。ところが、駅を離れて8分ほど経ったあたりで、ぼくは急激に猛烈な便意をもよおした。駅に戻ってするべきか、その彼の家まで我慢するべきか、判断に迷う地点である。周囲にコンビニなどは見当たらない。十歩進んで、やっぱり駅前に戻ろうと結論に至った。万一漏らししてしまった場合、目撃者は知り合いより、見知らぬ人のほうがマシだろう……。
方向転換と同時にプヒ、と尻が絶望の音を鳴らす。肛門の周辺は、あきらかにウエットさを帯びている。さっきの飲み会は焼き肉だった。ぼくは肉にあまり火を通さず、ほとんど生焼けの状態で口に運んでしまう。マッコリも、しこたま飲む。だからぼくは焼肉屋に行けば決まって腹がゆるくなる。
もう駅までは持たない、と観念した。まわりを見渡してみると、うしろの方向、つまりその彼の家がある方向に小さな葱畑があった。23区内とはいえ、まだ田園風景ののどかさを残した地域だ。街灯の照らす光は弱々しく、注視しなければ人が葱に混じっていても気がつかない……かもしれないぐらいには、薄暗い。
肛門を引き締めたつま先走りでぼくはその畑に近づき、申し訳程度に装備されている防犯ネットをくぐって不法侵入する。そして、震える手でズボンとパンツを下ろして、規則正しく整列した葱に同化するかのようにしゃがみ込み、一気に用を済ます。ほ~っ……とつく長い一息は、まるで毛穴中から染み出るようだった。
その彼の家へと向かう一本道は、まばらとはいえ、何人かの人が歩いている。
「ねぎだ! ねぎになるんだ!!」
丸出しの尻を突き出しながらぼくは自分にこう念じ、人通りが途切れるのをじっとやり過ごす。

5分ほど経って、ようやく人の気配がなくなったのを確認したあと、次にパンツとズボンをしゃがんだまんま確認する。幸いなことにズボンにまで被害は及んでいない。しかし、パンツは相当やばいことになっていた。その場で脱ぎ捨てていくしかなかった。
駅まで戻って、駅前のローソンで新しいパンツを買い、トイレを借りて履き替えてから、ふたたび友人の家へと向かう。葱畑に近づくにつれ、やるせない罪悪感にぼくは襲われる。畑の前で手を合わせ、頭を下げる。肥やしになるから、ごめんなさい……。
パーティーは朝までおおいに盛り上がり、その彼の自宅のソファで目を覚ましたのは朝の10時すぎだった。やり残している仕事があったので、まだ寝ている者たちを起こさぬよう、そっと家を出る。
仕事をするにはもったいないほどの晴天だった。夜には気がつかなかったが、整備された公園、大きな庭を構えるお屋敷……と、至る処に緑がいっぱいで、空気も心なしか、美味しい。
約12時間前の忌まわしい出来事もすっかり忘れ、清々しさに浸りつつ散歩気分を楽しんでいると、また昨日の葱畑へとたどり着く。葱の群列のなかに、段ボールで作られた一本の立て札が立っていた。その立て札にはこう書かれていた。
「ココで大便した人間は地獄に堕ちろ!」
……辛うじて勃起を保っていた性器がとうとう萎えてき出している。とにかく一刻も早く家に帰りたかった。家には恋人が待っている。男と上手に付き合う術を知らず、その些細な会話のやりとりを懸命に学ぼうとする、おかえりを言い慣れない女だった。

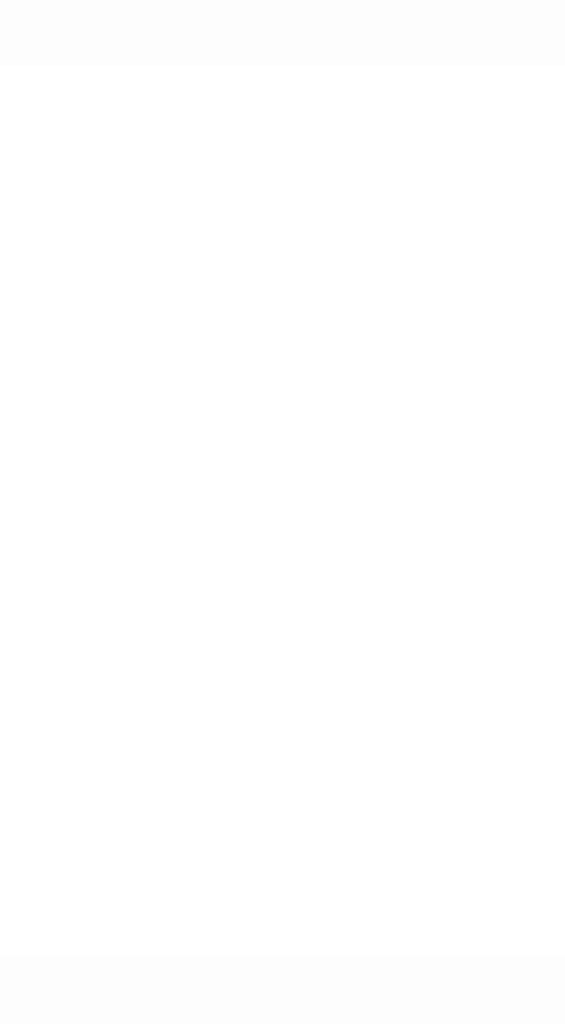
小説家の役割は、
下すべき(最低限の)判断をもっとも
魅惑的なかたちにして
読者にそっと手渡すことにある
── 村上春樹 ──
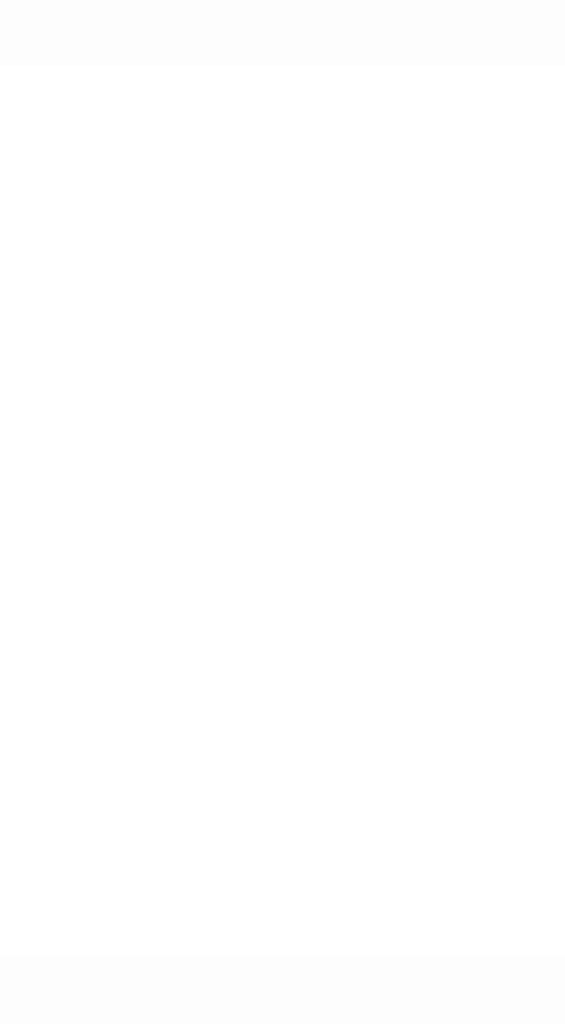
「ヨシダさん……ですか?」
ミカコと名乗る女は、電鉄会社が運営する、大井町駅中央口からすぐそばにある小ぎれいなビジネスホテルのロビーのソファに座っているぼくに、背後からこう声を掛けてきた。
女は30代後半から40代前半あたりの年頃で、身長からも容姿からも肉付きからもメイクにも際立った特徴を見いだすことができない、いわゆる地味めなタイプだった。膝丈くらいの紺のワンピース姿で、小ぶりなサイズの真珠をアクセントとするゴールドチェーンのネックレスが、控えめに胸を飾っていた。ぼくは白いVネックのTシャツをインナーにして、3年ほど前に御殿場のアウトレットのHUGO BOSSで購入した一張羅の黒いスーツを着ている。「できれば遊びにも冠婚葬祭にも使えるものを」という貧乏臭い理由で選んだ、葬式用にはさすがにきびしい、光沢感が強いウール素材でつくられた細身のスーツで、値段は上下総額で8万円するかしないかだったと思う。まだ10月初めの陽気には季節外れで首筋にうっすら汗がにじんでくるが、一張羅なのだからしかたない。
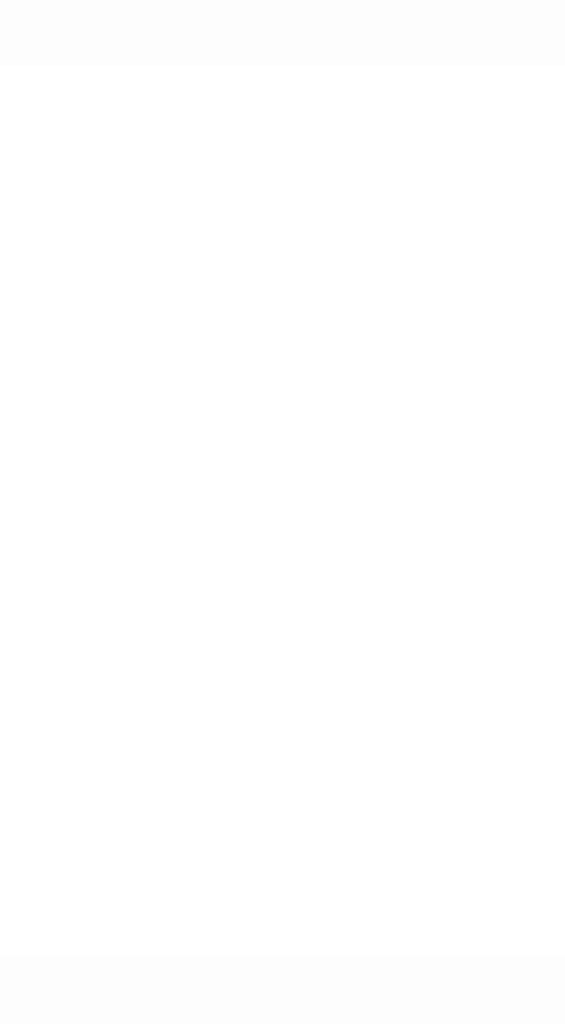
半年前の4月、ぼくがウェブデザイナーとして専属契約していた新進のIT企業がなんの前ぶれもなく倒産し、CEO、COO、CFOの肩書きが名刺に刷られた3人の幹部連中は全員夜逃げした、らしい。
当然、すでに納品した仕事のギャラは振り込まれず、クレジットカードやキャッシングでしのげるその場をしのいでいたものの、ぼくは現金に困っていた。とりあえずは、一週間後に約20万円の支払いが迫っているのだ。
途方に暮れたぼくは気がつくと、渋谷の裏通りに雑然と建ち並ぶ怪しげな貸しビルの壁面に貼ってあった「出張ホスト募集」のビラに記載されている電話番号を半ば夢遊病者ごとくタップしていた。もし、必要経費などと手付け金のような前払いを請求されたり、「研修」と称する面倒な召集を強要されたりしたら、その時点で断りを入れるつもりだった。ビラ上には「週1回でも可」「1日4時間以下勤務」「月収30万以上保障」……と、お決まりのキャッチコピーが、けばけばしくおどっている。
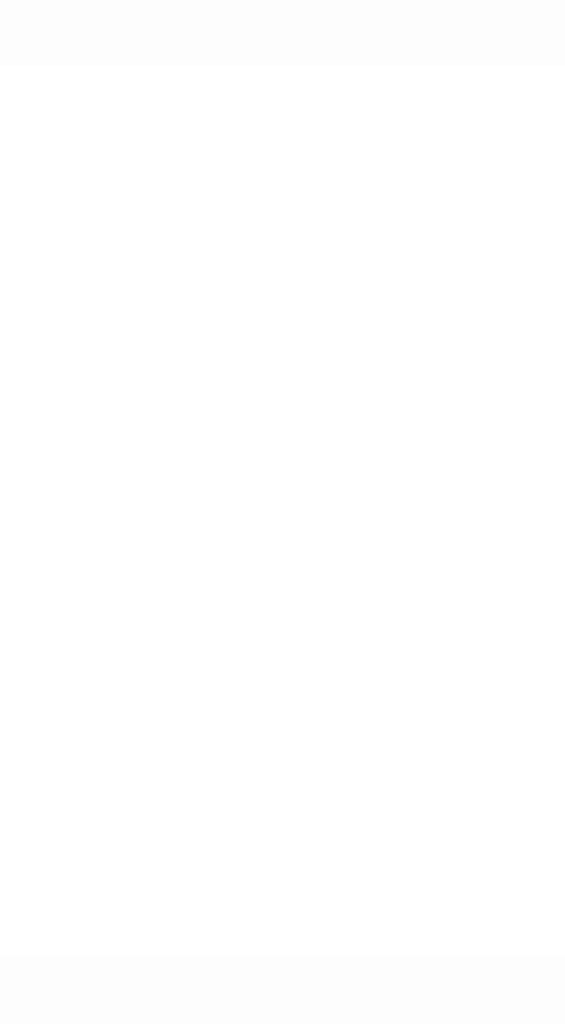
臆病なまでに身構えるぼくの予想に反し、入会はあっけないものだった。前払いも研修もなく、面接すらネットでのやりとりだけで済んだ。「女性の嫌がる行為はやめてください」「連絡先の交換は厳禁」ほか、いくつかの簡単な注意事項に、ここ数日のスケジュールや報酬の受け渡し方法の確認のみで、申告したぼくの個人情報も、プロフィール写真以外はほぼでたらめだ。「こんなに杜撰で大丈夫なのか?」と、別の不安が頭をよぎる。
入会後わずか2日後に、いきなり依頼の電話がかかってきた。
「ミカコさんという女性が、ヨシダさん(もちろん偽名だ)をご指名されたので、明日の18時に大井町駅の○○ホテルのロビーへ来てもらうことは可能でしょうか?」
快活と事務的のバランスが絶妙な、20代にも50代にも聞こえる男性の声だった。
「大丈夫です。ぼく当日黒いスーツを着ていく予定で、年齢は42歳ですけど、見ためは30代だと周囲からはよく言われます」と答えたら、「そうなんですか」と苦笑混じりに流された。肩の力が抜け、ぼくは軽口をつづける。
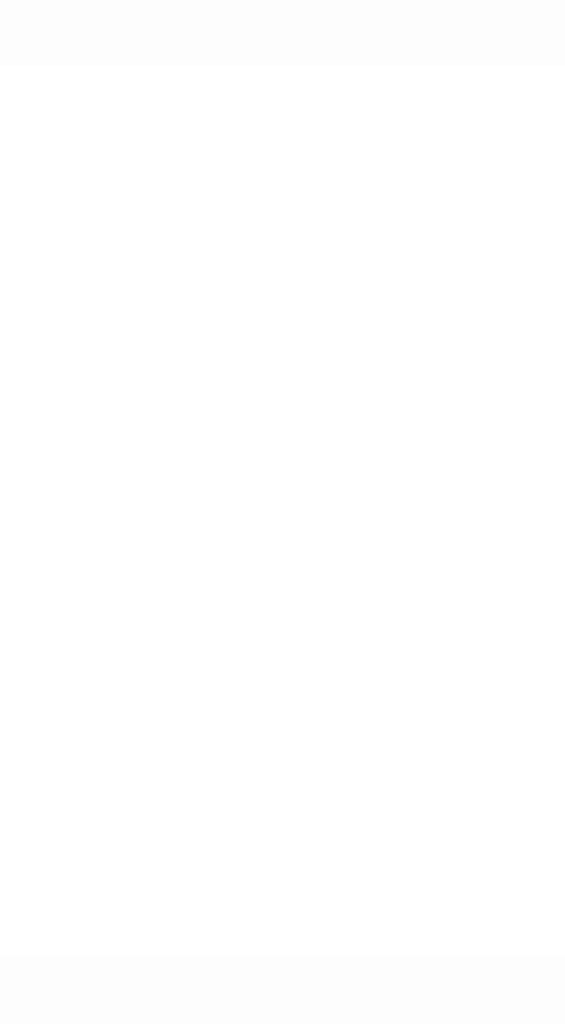
「新宿の京王プラザだとか六本木のマンダリンとかを想像していたんですけど……大井町って、かなりマニアックですよね?」
「先方様のご都合なので……」
「それにしても、こういうのって本当にホテルのロビーで待ち合わせするんですね?」
「なんだかんだ言って、ホテルのロビーはこういう待ち合わせに最適なんですよ」
「まずは食事に行きますか?」
できるだけの優しい口調でぼくは訊ねてみる。すると、ミカコと名乗る女はうつむきながらかすかに首を横に振り、こう短くささやいた。
「最初からホテルでいいです……」
「上の部屋を取っているんですね」
「いや、歩いてちょっとのところにラブホテルがありますから……」
ロビーを出て、ミカコと名乗る女の半歩あとを、ぼくは無言のままついていく。肩でも抱いたほうが良いのかと迷いもしたが、やめておいた。ぎこちない空気は動かすよりもキープしておいたほうがやや無難だ、と瞬時に判断したからだ。
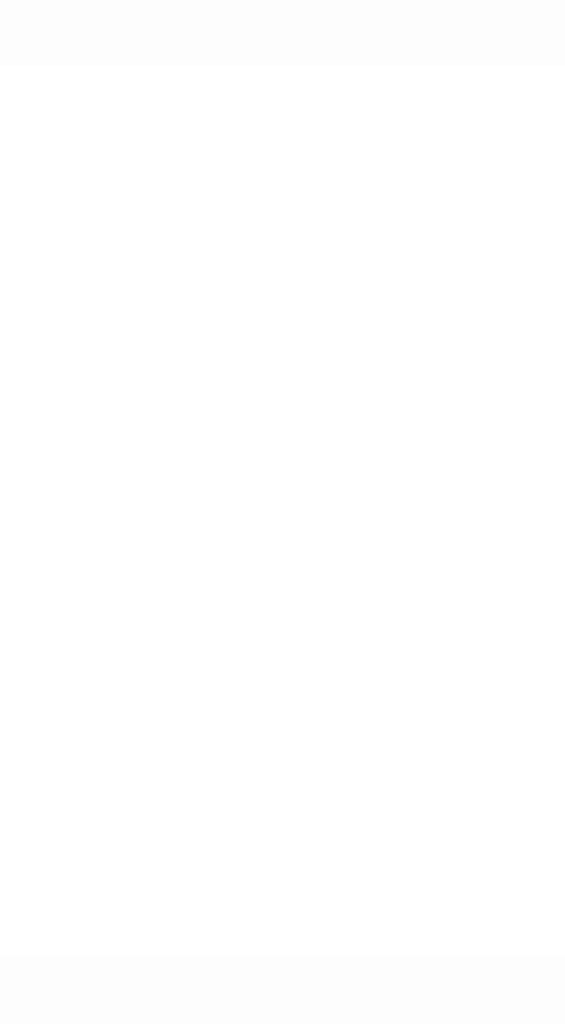
大井町駅の中央口から西口まで徒歩で移動して、京急の青物横丁駅方面に向かう商店街を通り、ゼームス坂を左に折れる。なぜこのヒトはこうも一目散に、わき目もふらずにぼくをナビゲートできるのだろう、意外とこういうサービスを利用し慣れているのか、それとも住まいが近所なのか……そんなことを考えながら雑多な飲食店が並ぶ横丁を通りすぎてまもなく、車がぎりぎり一台入れるだけの幅しかない小径を、また右に曲がる。閑静で古い住宅街だ。こんなところにラブホが本当にあるんですか、と聞かずにはいられなくなったころ、左側に三階建ての、濃いクリーム色の壁面で窓の上に赤と白のツートンカラーで彩られた雨避けが付いた、まるでヨーロッパの田舎町にぽつんと佇む萎びたペンションのようなラブホテルが目に入り、ミカコと名乗る女がそのエントランスを躊躇する様子も見せずにくぐっていく。一応、ライトアップはされているものの、「この建物内にいるカップル全員がセックスをしている」というラブホテル独特の、ぐらぐらに煮立った天ぷら油が放つ熱気のようなオーラはまったく漂っていない。「OPEN」と「FULL」を青と赤で表示する電飾板は、早秋午後六時の闇空にもかかわらず、見分けがつかなかった。
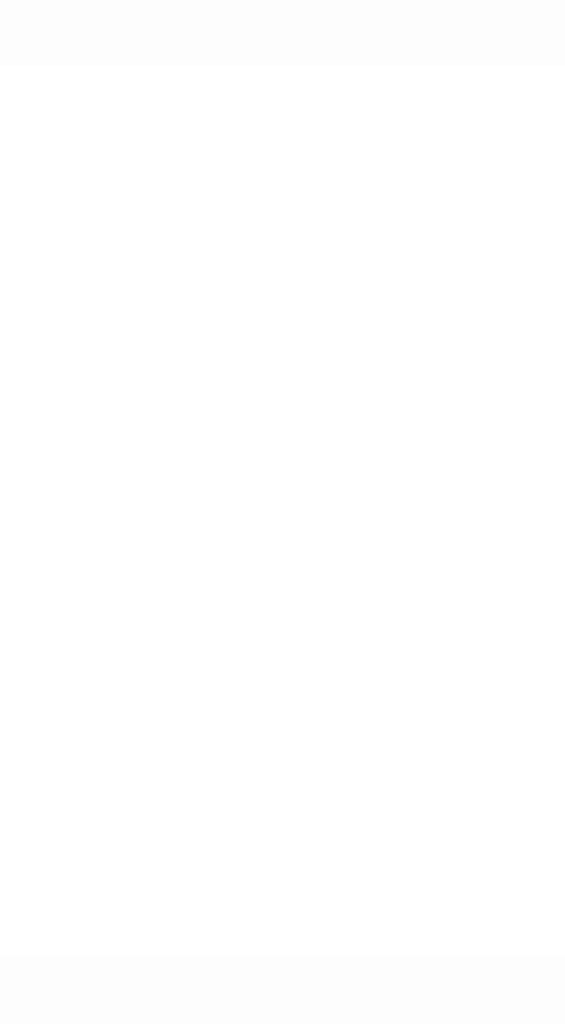
ミカコと名乗る女は、電鉄会社が運営する小ぎれいなビジネスホテルのロビーで会ったときの印象に反して、均整がとれた滑らかな曲線がなまめかしい、完璧な身体の持ち主だった。肌も吸いつくように纏わりついてきて、しかも貪欲で、すぐさま猛烈に勃起する。
それでもぼくは何故かなかなかいけなかった。ちょうど、一つしか小便器がない公衆トイレで、後方に並ぶ行列を意識しながら用を足さねばならない感覚に似ている。射精が“強要”を通り越して“義務”と化している初めての経験に焦り、戸惑っているのかもしれない。
もはや集中力を欠いた状態で腰を振りつづけるぼくは、なにか難しいことを考えて、それを猥褻へと結びつけてみようと試みた。
100万年前に生きていた人類は、鋭く尖った石器を代表とする“道具”を使用していたにもかかわらず、大きな獲物を狩ることは稀で、おもに植物を集め、昆虫を捕まえ、小さな動物を追い求め、他のもっと強力な肉食獣が残した死肉を、たとえばライオンがキリンを倒しハイエナやジャッカルがその残り物を漁ってからの“おこぼれ”を食らっていたという。
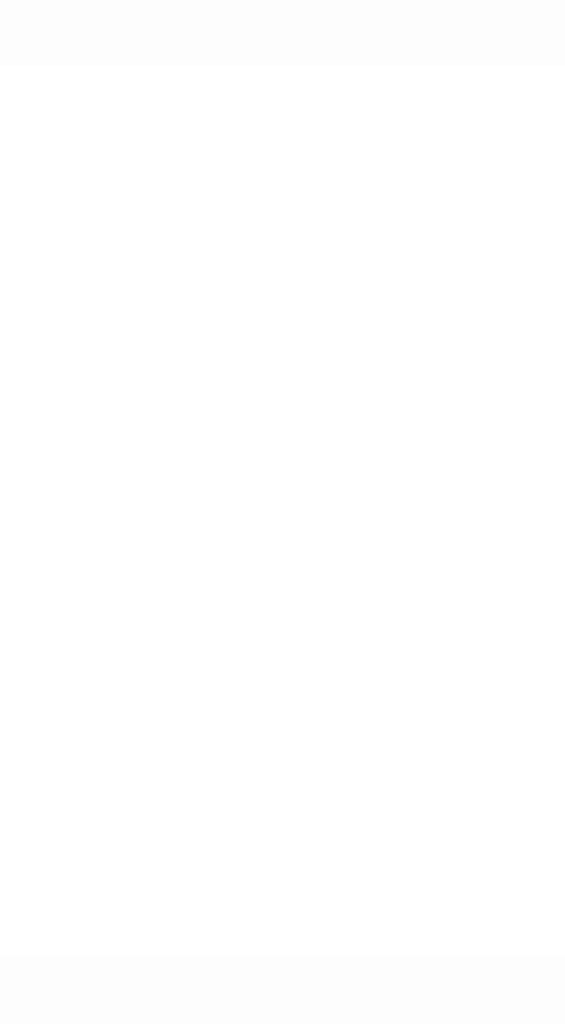
石器を代表とする“道具”の最大の用途の一つは、骨を割って中の骨髄をすすることだったのだ。長年、このように食物連鎖の中間を占めていた人類が頂点へと飛躍したのは10万年前のホモ・サピエンスの台頭に伴っており、その道のりにおける重大な進化とは「火を手懐けたこと」であった……道具に頼ってインターバルを……と、ふいにアイディアが浮かんだが、あいにく道具は持ち合わせていなかった。部屋の設置されている小型の冷蔵庫のような自動販売機で数種の道具は販売いてはいるものの、とてもじゃないが行為を中断してそれを購入する決断は、ぼくには下せない。あきらかにタイミングを逃している。また別の難しいことを懸命に脳内の引き出しからまさぐる作業を繰り返す。
ボノボは、まずメスが、相互に尻と性器をこすり合わせるような、ホカホカと呼ばれる性的接触をしたあとで獲得した蜂蜜を順番に分ける。争奪の競争や衝突は起こらない。食物分配の主導権はメスが握っている、オスには余剰分が最後に分配される。なんて素晴らしい世界なんだ……でも、やはりだめだった。空白となった思考のすき間を、逆に生理的現象の我慢を強いるシチュエーションの記憶がじわじわと潜り込み、やがて一つの大きな流れへと変わっていく。
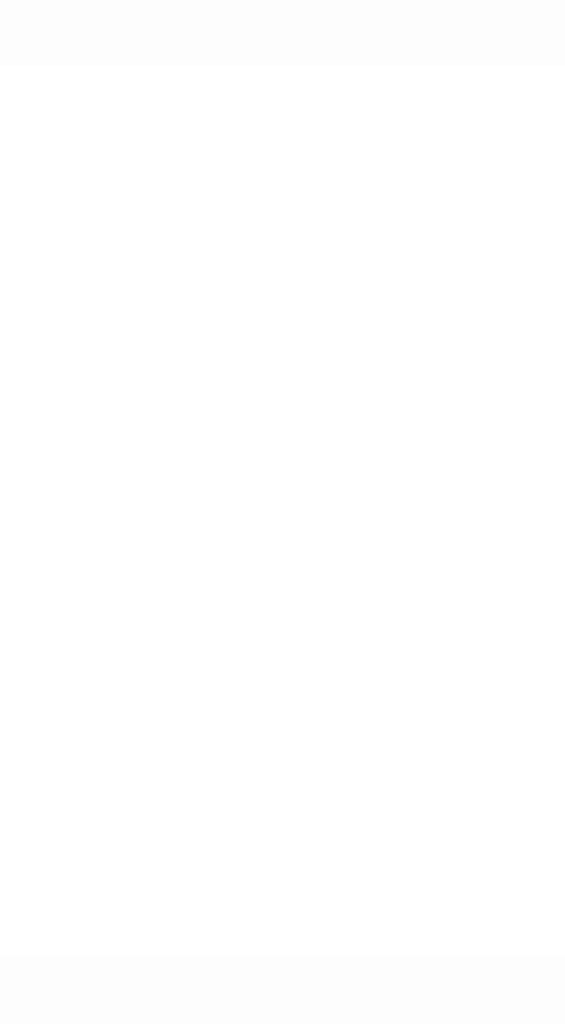
とある週末の夜、とある男友だちの家へ遊びに行ったときの話だ。
ささやかな宅飲みパーティーがあるということで、ぼくはそこに急いで合流しようとしていた。その日は別の飲み会にも顔を出してきた直後で、最寄りの駅に着いたころは、すでに夜の11時を過ぎていた。
その彼の家は、駅から延びる真っすぐの道沿いにあって、Googleマップを使わずとも間違えようもなく、だが徒歩だと15分はかかってしまう、距離的には微妙な場所だった。最終のバスがなくなったのか、駅前ロータリーのタクシー乗り場には行列ができている。
酔い醒ましにいいな、と歩いて行くことにした。ところが、駅を離れて8分ほど経ったあたりで、ぼくは急激に猛烈な便意をもよおした。駅に戻ってするべきか、その彼の家まで我慢するべきか、判断に迷う地点である。周囲にコンビニなどは見当たらない。十歩進んで、やっぱり駅前に戻ろうと結論に至った。万一漏らししてしまった場合、目撃者は知り合いより、見知らぬ人のほうがマシだろう……。
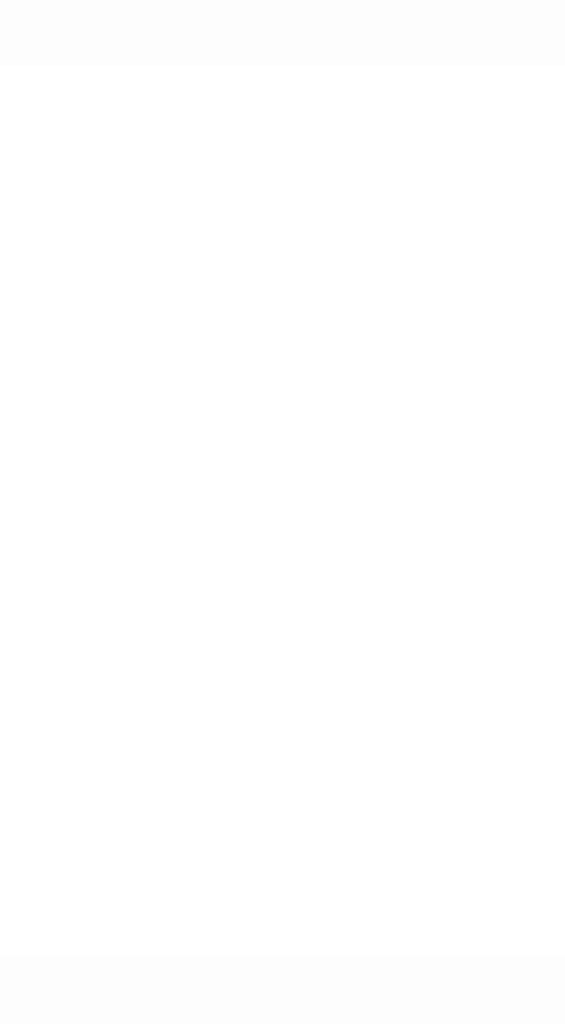
方向転換と同時にプヒ、と尻が絶望の音を鳴らす。肛門の周辺は、あきらかにウエットさを帯びている。さっきの飲み会は焼き肉だった。ぼくは肉にあまり火を通さず、ほとんど生焼けの状態で口に運んでしまう。マッコリも、しこたま飲む。だからぼくは焼肉屋に行けば決まって腹がゆるくなる。
もう駅までは持たない、と観念した。まわりを見渡してみると、うしろの方向、つまりその彼の家がある方向に小さな葱畑があった。23区内とはいえ、まだ田園風景ののどかさを残した地域だ。街灯の照らす光は弱々しく、注視しなければ人が葱に混じっていても気がつかない……かもしれないぐらいには、薄暗い。
肛門を引き締めたつま先走りでぼくはその畑に近づき、申し訳程度に装備されている防犯ネットをくぐって不法侵入する。そして、震える手でズボンとパンツを下ろして、規則正しく整列した葱に同化するかのようにしゃがみ込み、一気に用を済ます。ほ~っ……とつく長い一息は、まるで毛穴中から染み出るようだった。
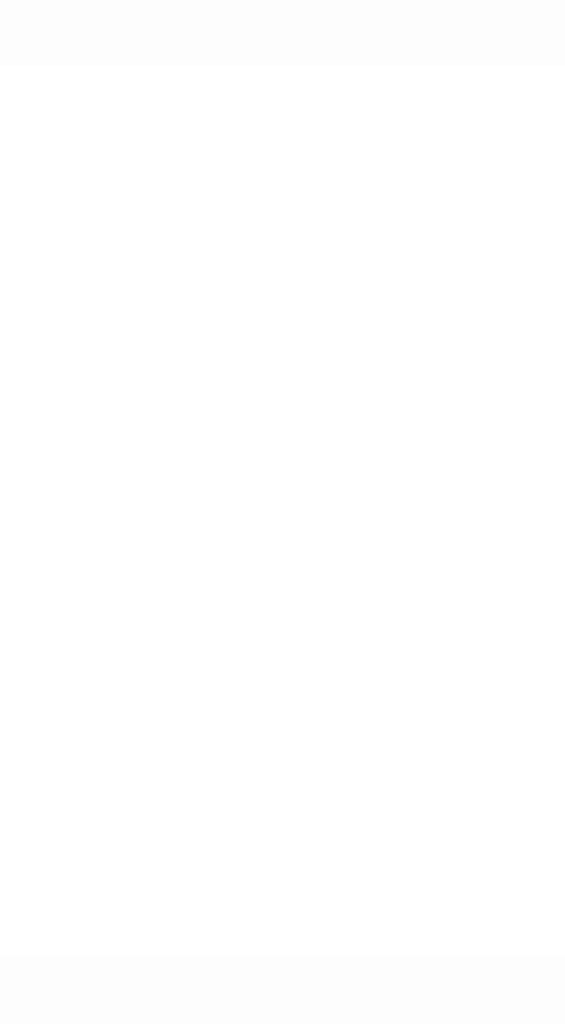
その彼の家へと向かう一本道は、まばらとはいえ、何人かの人が歩いている。
「ねぎだ! ねぎになるんだ!!」
丸出しの尻を突き出しながらぼくは自分にこう念じ、人通りが途切れるのをじっとやり過ごす。
5分ほど経って、ようやく人の気配がなくなったのを確認したあと、次にパンツとズボンをしゃがんだまんま確認する。幸いなことにズボンにまで被害は及んでいない。しかし、パンツは相当やばいことになっていた。その場で脱ぎ捨てていくしかなかった。
駅まで戻って、駅前のローソンで新しいパンツを買い、トイレを借りて履き替えてから、ふたたび友人の家へと向かう。葱畑に近づくにつれ、やるせない罪悪感にぼくは襲われる。畑の前で手を合わせ、頭を下げる。肥やしになるから、ごめんなさい……。
パーティーは朝までおおいに盛り上がり、その彼の自宅のソファで目を覚ましたのは朝の10時すぎだった。やり残している仕事があったので、まだ寝ている者たちを起こさぬよう、そっと家を出る。
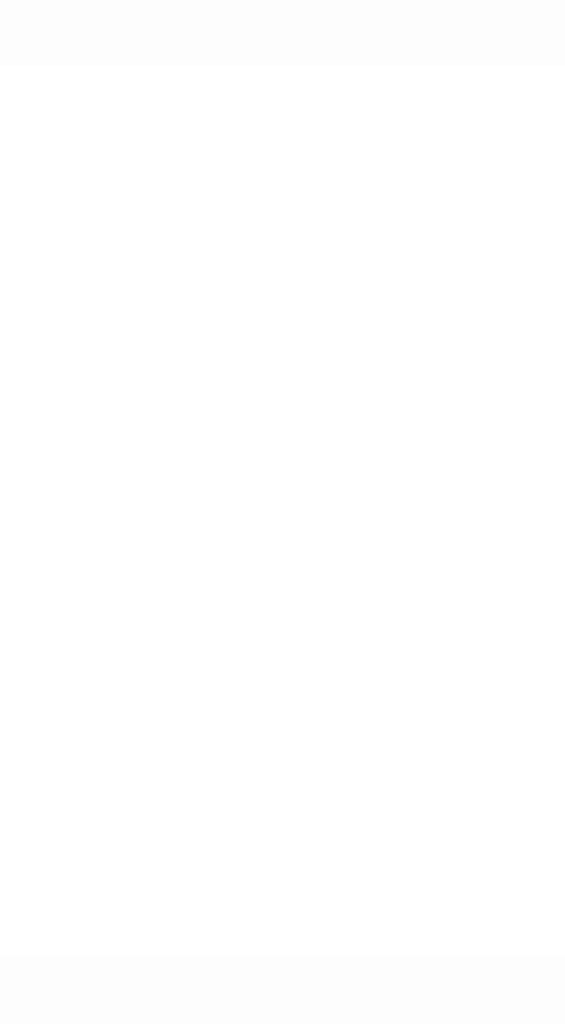
仕事をするにはもったいないほどの晴天だった。夜には気がつかなかったが、整備された公園、大きな庭を構えるお屋敷……と、至る処に緑がいっぱいで、空気も心なしか、美味しい。
約12時間前の忌まわしい出来事もすっかり忘れ、清々しさに浸りつつ散歩気分を楽しんでいると、また昨日の葱畑へとたどり着く。葱の群列のなかに、段ボールで作られた一本の立て札が立っていた。その立て札にはこう書かれていた。
「ココで大便した人間は地獄に堕ちろ!」
……辛うじて勃起を保っていた性器がとうとう萎えてき出している。とにかく一刻も早く家に帰りたかった。家には恋人が待っている。男と上手に付き合う術を知らず、その些細な会話のやりとりを懸命に学ぼうとする、おかえりを言い慣れない女だった。